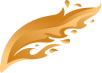重要なポイント
ビデオゲームにおける"クロス〇〇"とは、ゲーム体験を向上させるために導入された機能群のこと。"クロスプレイ"は異なるハード間でのオンライン対戦や協力、"クロスプラットフォーム"は複数ハードでの展開、"クロスセーブ"は異なるハード間でのセーブデータ共有、"クロスプログレッション"は進行状況をアカウントに紐付けること、"クロスジェネレーション"は前世代機・現世代機での同時展開を指します。
さまざまなゲームで遊んでいると、たびたび目にする"クロス〇〇"という言葉。その作品の特徴のひとつとして挙げられることもあれば、ときにセールスポイントとして用いられることもある。
本記事ではクロスプレイ、クロスプラットフォーム、クロスセーブ、クロスプログレッション、クロスジェネレーションの、5つの"クロス〇〇"を解説する。
<クロスプレイとは>ハードの垣根を超えたオンラインプレイ
異なるゲームハード(ゲーム機)間のユーザーどうしでも、対戦や協力プレイを楽しめるのが"クロスプレイ"。おもにオンラインプレイが採用されているタイトルに用いられる用語だ。プレイヤーそれぞれハードを統一する必要がなく、ユーザーどうしが異なるゲーム機で対戦・協力プレイを楽しめるのが大きなメリット。
昨今では、家庭用ハードとPCのクロスプレイは標準的な機能として搭載されていることも多く、タイトルによってはモバイル版とのクロスプレイに対応している場合もある。
ただし、難点としてハードごとのゲームバランスが整っていないことも見受けられる。とくに対戦ゲームにおいてはバランスの悪さが問題になることもあり、タイトルによっては「このハードで遊んだほうが強い(勝ちやすい)」といった状況になる場合もある。
そのような部分を考慮し、"クロスプレイをオフにする"といったオプションを実装しているタイトルも多く存在する。
おもなクロスプレイ対応タイトル
- 『Fortnite』
- 『Rocket League』
- 『Apex Legends』
- 『ストリートファイター6』

『Apex Legends』。PC版に比べて、家庭用ハード版のほうが"エイムアシスト"(銃の照準の狙いを補助する機能)が強いため、クロスプレイ時の対戦バランス問題として語られやすい。
<クロスプラットフォームとは>複数のハードでタイトルを展開
ひとつのタイトルを、複数のハードで発売・配信するのが"クロスプラットフォーム"。"マルチプラットフォーム"と呼ばれることもある。
"クロスプレイ"と異なり、オンラインプレイを介さない場合でも用いられる。多くのタイトルはクロスプラットフォーム展開をしているが、Nintendo Switch専用タイトルなど、そのハードでしか遊べないタイトルも多数存在する。
プレイヤーが対応するハードさえ持っていれば遊べるのが大きなメリット。ゲームメーカー側も、なるべく多くのプレイヤーで遊んでもらうために、昨今はクロスプラットフォーム展開を採用している作品も多い。
基本的にはそのゲームの持つ魅力を味わえるようになっているが、タイトルによってはハードの特性やスペックに合わせた調整やアレンジが加えられているため、若干体験が異なる場合もある。
たとえばプレイステーション5と、プレイステーション4ではマシンスペックが大きく異なるので、グラフィック品質やロード時間などが体験の違いとして挙げられる。
おもなクロスプラットフォーム対応タイトル
- 『Minecraft』
- 『Among Us』
- 『原神』
- 『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

『Minecraft』。リリース以降、ほとんどのハードを網羅する展開をしており、Wii U版やプレイステーション3版なども存在する。
<クロスセーブとは>セーブデータをハード間で共有
ゲームのセーブデータを、遊ぶハードを変えても共有・転送して利用できる"クロスセーブ"。とくに"モバイル・携帯ハード"と"PC・家庭用ハード"で同時展開するタイトルに採用されることも多い。
たとえばRPGならば、外出先において"モバイル・携帯ハード"で遊んだ冒険をセーブしておけば、家に帰ってきてから"PC・家庭用ハード"で続きを楽しめる。同じように、部屋のソファーに寝そべりながら"モバイル・携帯ハード"で遊んだゲームの続きを、大型モニターに繋いだ"PC・家庭用ハード"で再開することも可能だ。
このように、プレイヤーのライフスタイルに応じて、同じゲームを異なるハードで交互に遊ぶにはうってつけのシステムとなっている。
なお、オンライン専用ゲームの場合はセーブデータをゲーム機のハードディスクではなく、インターネットサーバーに保存するケースがほとんど。ハードが異なっても同じゲームアカウントならば、ゲーム進行データを共有できることもある。これは、正確には次に説明する"クロスプログレッション"機能とも言えるのだが、たとえば『Destiny 2』ではそれを"クロスセーブ"と呼称しているため、タイトルによって定義は曖昧な部分もある。
おもなクロスセーブ対応タイトル
- 『Destiny 2』
- 『サイバーパンク2077』
- 『No Man's Sky』
- 『遊戯王 マスターデュエル』

『No Man's Sky』。発売時は対応していなかったが、のちにアップデートでクロスプレイ、クロスセーブなどが追加された。、
<クロスプログレッションとは>ゲームデータをひとつのアカウントに統一
プレイヤーのゲームアカウントに、セーブデータやゲーム進行状況などを紐づける"クロスプログレッション"機能。おもに複数ハードで展開している"マルチプラットフォーム"ゲームで採用されていることが多い。
冒険の進行であったり、対戦の戦績などがひとつのアカウントに結び付くため、ハードを変えてプレイしても、自分のデータとして保存されるのが特徴。
クロスセーブに近い機能だが、あらゆる情報やアイテムを、すべてのハードで共有できるのがポイント。おもにオンラインゲームや、対戦ゲームで使用されている。一部のオンライン専用ゲームは、特別な設定などを必要とせずにクロスプログレッションに対応していることも多い。
ちなみにモバイルゲームでは、機種変更やアカウントの紛失などに対応するために、そのゲーム専用のアカウントと、GoogleアカウントやSNSアカウントなど、別々のアカウントどうしを紐づけるシステムがある。昨今では当たりまえのように採用されている機能だが、これも"クロスプログレッション"のひとつだ。
プレイヤーのデータはサーバーに保存されているので、紐付けたアカウントでログインすれば、PCとモバイルを使い分けて遊ぶこともできるほか、モバイルの機種変更やアカウントの復旧などにも利用できる。基本的には"ゲームの進行をすべてのハードで共有する"ことが機能のメインだが、アカウント管理がしやすくなるのも"クロスプログレッション"機能の魅力と言えるだろう。
おもなクロスプログレッション対応タイトル
- 『Call of Duty:Warzone』
- 『Dead By Daylight』
- 『VALORANT』
- 『The Witcher 3: Wild Hunt』

『VALORANT』。家庭用版とPC版で、それぞれランクなどの戦績のほか、銃の見た目を変更するスキンなどもデータ共有される。
<クロスジェンとは>前世代機と現世代機で同時展開
前世代のゲームハードと、現世代のゲームハードで同時発売するのが"クロスジェネレーション"(または"クロスジェン"とも呼ばれる)。
たとえば『Horizon Forbidden West』は、プレイステーション4とプレイステーション5で同時に展開されている。"あとからプレイステーション5版を制作した"のではなく、当初から別々に発売できるように、同時開発していたということだ。
これを"クロスジェネレーション"と呼ぶが、おもに海外で使われている用語である。日本のプレイヤーにはなじみが薄く、同じ意味合いで"縦マルチ(縦マルチプラットフォーム)"と呼ぶこともある。
おもなクロスジェン対応タイトル
- 『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』
- 『龍が如く8』
- 『Horizon Forbidden West』

『Horizon Forbidden West』。プレイステーション4版を買った人でも、あとからプレイステーション5版にアップグレードできるといったサポートもある。
"クロス〇〇"は、プレイヤーのための機能である
| 名称 | 機能 |
| クロスプレイ | ハードの垣根を超えたマルチプレイ |
| クロスプラットフォーム | 複数のハードでゲームを展開 |
| クロスセーブ | ゲームの進行データを各ハードで共有 |
| クロスプログレッション | プレイ状況をアカウントに紐付け各ハードで共有 |
| クロスジェネレーション | 前世代機・現世代機、両方のハードで展開。いわゆる"縦マルチ" |
まとめると、どの機能もタイトルそれぞれが持つ"根本の遊び"自体に影響する部分は少ない。つまりプレイヤーの"遊びやすい環境を整える"ための機能となっている。
ゲーム体験を向上させるために、ゲームメーカー側が用意したサービスの数々である。言ってみれば、ゲームプレイにおけるサポート機能ではあるが、同時にセールス部分にも影響する要素とも言えるだろう。そのぶんメーカー側には、高い技術力や手厚いサポートが求められる。